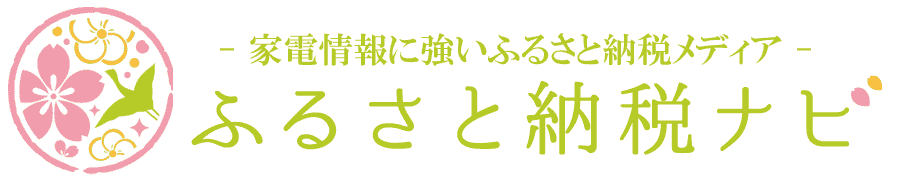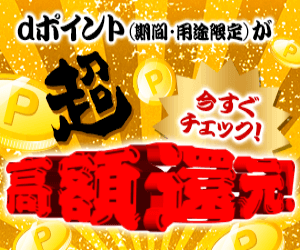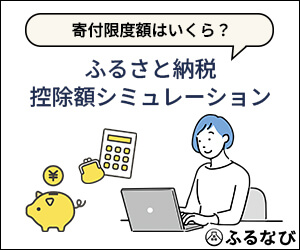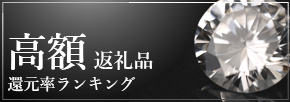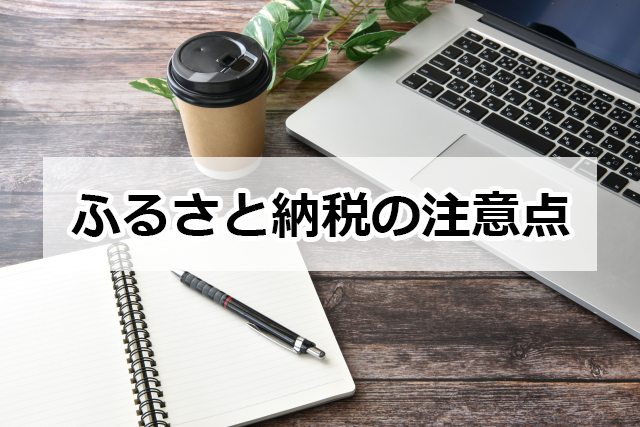
ふるさと納税、10の注意点。同じ自治体への寄付や住所、ワンストップなどの疑問にお答えします
「お得な制度」として知られるふるさと納税。しかし「いろいろ手続きがあって、難しそう…」と思っている方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、ふるさと納税で押さえておきたい10の注意点について解説します。
これらの点に注意すれば、ふるさと納税制度をお得に活用できます。
物価高の昨今、税金控除が受けられ、返礼品ももらえるふるさと納税をぜひ活用してください。
目次
ふるさと納税の注意点1:控除申請手続きを忘れずに
ふるさと納税では、税金の控除を受けられることが大きなメリットです。
しかし寄付をしただけで自動的に控除が受けられるのではなく、寄付後に控除を申請する必要があります。
大手ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」が2025年2月に発表した「ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査」では、ふるさと納税を活用している4人に1人が「寄附金控除を受けたことがない」と回答しています。
その理由は「手続きの仕方を知らない」「手続きが面倒だから」というものでした。
しかしふるさと納税の控除手続きは、むずかしくありません。特に、「ワンストップ特例制度」ならオンラインで完結する場合もあります。
ふるさと納税ナビでも控除手続きについて解説しているので、ぜひ参考にしてください。せっかく設けられている制度ですから、ぜひ税金の控除を受けましょう。
ふるさと納税の注意点2:寄付は控除上限額の範囲内で
ふるさと納税では、「1年間の総寄付金額ー2,000円」の額が、寄付をした年の所得税や翌年の住民税から控除されます。
寄付できる金額に制限はありませんが、税金から控除される金額には上限が設定されています。この上限額は「控除上限額」と呼ばれます。
控除上限額は総務省が定めており、年収や家族構成などの条件にもとづいて段階的に異なる金額が決まっています。
控除上限額を超えた分の寄付は控除されない
控除上限額を超えて寄付をした分の金額は税金からは控除されず、「純粋な寄付」となります。
このため、自分の控除上限額をあらかじめ知っておき、控除上限額の範囲内で寄付をすることが、ふるさと納税制度をお得に活用するポイントとなります。
控除上限額を試算できる「シミュレーター」
控除上限額の計算式は複雑ですが、「シミュレーター」を使うと簡単に試算することができます。
あなた(寄付者様)の給与収入必須
あなたの家族構成必須
シミュレーション結果
までのふるさと納税が控除の目安となります。
- 本フォームは総務省ポータルサイトの早見表に基づき設計しております。総務省ポータルサイトの早見表はこちら。
- シミュレーション結果はあくまで寄付上限額の目安となります。
より正確な金額を知りたい場合はお住まいの自治体もしくは税理士等にご相談ください。 - シミュレーション結果に関する、何らかのトラブルや損失、損害等が発生した場合にも、一切の保証をいたしかねます。
また楽天ふるさと納税の「詳細版シミュレーター」を使うと、住宅ローン控除や医療費控除、iDeCoなども考慮した控除上限額の試算ができます。
ふるさと納税の注意点3:同じ自治体に複数回寄付するとき
ふるさと納税では、1年の間に同じ自治体に複数回寄付をすることも可能です。
ただし自治体によっては、年間の返礼品の受け取り回数に「1年間に1回のみ」などの制限を設けている場合もあります。
例えば返礼品の受け取り回数が「年1回」となっている場合では、2回目以降の寄付では返礼品は発送されません。
しかしこの場合も、その寄付額を控除の申請に含めることができます。
返礼品がもらえないこともある
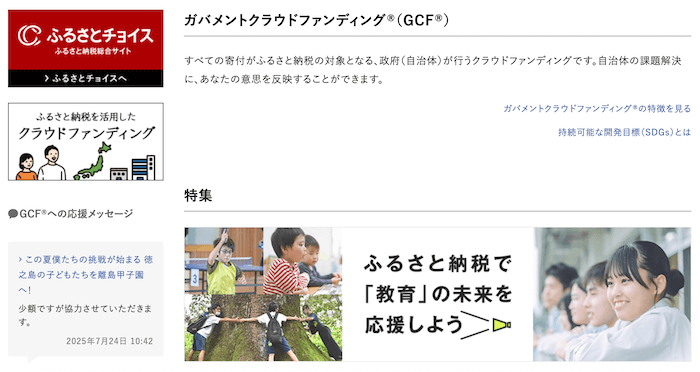
ふるさと納税の寄付では、返礼品がもらえない場合もあります。
例えば、自分の住民票登録のある自治体に寄付をすることは可能ですが、返礼品はもらえません。
具体的には、「住民税決定通知書」に記載されている「都府県税」と「市区町村税」の納税先への寄付では返礼品がもらえません。
また、寄付の種類によっては返礼品の用意がない場合もあります。
例えば、以下の場合が該当します。
・災害支援が目的の寄付
・ふるさと納税とクラウドファンディングが合体した形の「ガバメントクラウドファンディング」の一部のプロジェクト
・ふるさとチョイスの思いやり型返礼品プロジェクト「きふと」の一部
・「「お礼の品とポイント」不要の寄付をする」を選択した場合(ふるさとチョイス) など
ふるさと納税の注意点4:住民票住所が現住所と違う場合は?
ふるさと納税では「年間の総寄付金額ー2,000円」の額が所得税と住民税から控除されるため、寄付申し込みの際に記載する住所は、課税地の住所と同一である必要があります。
住民票の住所と課税地が異なる場合は、自治体により必要な手続きが異なるため、課税地の自治体にお問い合わせください。
通常は、住民票のある市区町村から住民税が課税されます。しかし何らかの理由で住民票を異動せず、単身赴任するなど長期で住まいを別の市区町村に移している場合は「居住実態がある」と判断され、居住地の市区町村から課税される場合もあります。
ふるさと納税の注意点5:ワンストップ特例制度の注意点は?
ワンストップ特例制度を利用したい場合は、寄付先の自治体数や、申請書の提出期限などに注意が必要です。以下の点を確認しておきましょう。
利用の条件
ワンストップ特例制度は、以下の3点を満たす場合に対象となります。
・確定申告をする必要のない給与所得者等であること
・ふるさと納税以外にも、確定申告行う必要がない場合
・年間の寄付先が5自治体以内である
*同じ自治体へ複数回寄付した場合は「1自治体」としてカウントされます。
申請書の提出は1月10日必着
寄付をした年の翌年の1月10日までに、寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します。
同じ自治体に複数回寄付した場合でも、寄付ごとに毎回、申請書を提出する必要があります。
申請書は、1月10日までに自治体に到着している必要があります。
年末年始は自治体の役所が休みになるので、年末近くに寄付をした場合はなるべく早く郵送するようにしましょう。
返礼品によっては、オンラインでワンストップ特例制度の申請手続きが完結する場合もあります。返礼品の詳細ページに記載があるので、オンラインで手続きをしたい場合は、返礼品選びの際にオンライン手続きの可否に注意しましょう。
確定申告をすると、ワンストップ特例制度は無効に
ワンストップ特例制度の申請を行った後に確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請は無効となります。
このため、確定申告にて再度、ふるさと納税の控除の申請も行う必要があります。
例えば、ワンストップ特例制度の申請をした後に一定額以上の医療費が発生し、医療費控除の申請を行う必要が出てきた場合などがあてはまります。
ふるさと納税の注意点6:ふるさと納税後に引っ越しした場合
引っ越した場合に必要な手続きは、状況により以下のように分かれます。
返礼品が届く前に引っ越した場合

自治体の連絡先は、ふるさと納税ポータルサイトの自治体ページの「お問い合わせ先」、または返礼品の申し込み完了メールに記載されているお問い合わせ先をご参照ください。
返礼品を受け取り後、ワンストップ特例の申請書を提出前に引っ越した場合
基本的には、ワンストップ特例の申請時に新住所を記載します。
しかし自治体により対応が異なる場合があるため、寄付先の自治体に問い合わせることをおすすめします。
控除申請に関する手続き
控除の申請は、寄付の翌年1月1日時点の住民票の内容で行う必要があります。
寄付をした翌年の1月1日までに住民票を異動した場合は、以下の手続きを行ってください。
なお、寄付をした翌年の1月2日以降に住民票を異動する場合は、手続きは不要です。
・ワンストップ特例制度を利用する場合
寄付先の自治体に、住所変更の届出書を提出します。
届出書の用紙は、寄付先の自治体に送付を依頼するか、またはふるさと納税ポータルサイトからダウンロードすることで入手できます。
・確定申告を行う場合
確定申告書は、寄付をした翌年の1月1日時点の住民票に記載されている内容で行います。
確定申告書の提出先も、寄付をした翌年(確定申告書を提出する年)の1月1日に住民票がある住所の所轄税務署となります。
ふるさと納税の注意点7:寄付者と控除を受ける人の名義は同一
ふるさと納税では、税金の控除を受ける本人が、自分の名義で寄付をする必要があります。
ふるさと納税の寄付額の税金の控除は、寄付者本人の課税額に対して行われるためです。
このため、控除を受けたい本人が自分の名義で寄付を行い、控除の申請も寄付者本人が自分の名義で行う必要があります。
例えば専業主婦の方がご自分の名義で寄付をしても、ご主人は寄付額に対する控除は受けられないので、注意してください。
ふるさと納税の注意点8:年末の寄付で注意することは?
ふるさと納税の寄付額をその年の税金に対する控除額に含めたい場合は、その年の12月31日までに寄付を行う必要があります。
このため、年末は寄付が集中します。
したがって年末の時期は、返礼品の品切れが多くなります。欲しい返礼品がある場合は、早めに申し込みましょう。
特に12月31日は寄付が集中するため、各ふるさと納税ポータルサイトの動作が重くなったり、決済エラーが生じたりする場合があります。
また、12月31日より前に年内の寄付申込受付を締め切る自治体もあります。
寄付はなるべく余裕を持って、早めに済ませることがおすすめです。
ふるさと納税の注意点9:返礼品選びで注意することは?
ふるさと納税では「寄付金額ー2,000円」の額が税金から控除されるため、「税金を前払いしている」ことになり、節税にはなりません。
しかし、控除に加えて自治体から返礼品ももらえます。つまり「実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえる」と考えることができ、返礼品の分、お得だといえます。
ただし、返礼品の「お得さの度合い」は返礼品により異なります。「お得さの度合い」を示すのが還元率で、還元率の数値が高いほど、その返礼品はお得だといえます。
ふるさと納税納税ナビ編集部では人気返礼品の還元率を調査し、ランキングを作成しました。
高還元率の返礼品を見つける際の参考にしてください。
ふるさと納税の注意点10:返礼品は「一時所得」に該当
ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、「一時所得」に該当します。
一時所得には最高50万円の特別控除額があるので、その年中の他の一時所得も含めた「一時所得の合計額」が50万円を超えなければ、所得税は発生しません。
総務省が「返礼品の還元率は3割以下とする」と定めているので、返礼品の実売価格が寄付金額の3割程度になるよう設定されていることが多いです。このため目安として、ふるさと納税の寄付を150万円程度以上行う際は、一時所得として申告が必要と考えるとよさそうです。
しかし返礼品によっては還元率が3割よりも高い場合があるので、注意が必要です。
また、ふるさと納税の返礼品以外にも一時所得がある場合は、ふるさと納税で高額返礼品を選ばなくても、一時所得の合計額が50万円を超えると課税されることになるため、注意してください。
まとめ
ふるさと納税制度をお得に活用するための、10の注意点をご紹介しました。
いくつかの注意点はありますが、ふるさと納税制度は地域を応援しながら素敵な返礼品がもらえるお得な制度です。ぜひこの記事を参考に、ふるさと納税制度を大いに活用してください。
この他にも、高還元率の返礼品や使いやすいふるさと納税ポータルサイトが見つかる記事、ふるさと納税制度をより良く理解するための記事などもご用意しています。あわせてぜひご覧ください。